
こんにちは!夫婦ブロガー、MANAです。
私たちのブログを見つけて下さり、ありがとうございます!
十二支と干支とは何のこと?

なぜ猫は干支に入っていないのかな?
十二支は、子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥という順番で、それぞれ鼠(ねずみ)、牛、虎、兎(うさぎ)、龍(りゅう)、蛇、馬、羊、猿、鶏(にわとり)、犬、猪(いのしし)という動物に対応しています。しかし、猫はこの十二支に含まれていません。なぜでしょうか?

今回はその謎について十二支の起源や伝説、様々な地域の文化の影響などあらゆる角度から解説していきます!
干支の起源
干支の起源は、中国殷の時代に遡ります。中国では干支「かんし」と読みます。
干支は、日・月・年のそれぞれに充てられ、60日(ほぼ2か月)、60か月(ほぼ太陰太陽暦5年)、60年などを表します。
干支は、十干と十二支を組み合わせたもので、十干は甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の10種類で、地支は子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥の12種類です。
干支は、中国を初めとしてアジアの漢字文化圏において、年、月、日、時間や方位、角度、ものごとの順序づけを表すのにも用いられます。

日本に暦が伝わったのは古墳時代からに飛鳥時代にかけてで、604年(推古12年)、日本最初の暦が作成されたと伝えられています。
日本の干支

日本においては「干支」を「えと」と読みます。ね、うし、とら、う、たつ…の十二支のみを指すことが多いですが、「干支」は十干と十二支の組み合わせを意味する言葉です。
「甲」「乙」「丙」「丁」などの「えと」という表現は、十干(じっかん)の命数法に由来します。これは、古代中国の天文学や陰陽思想に基づくもので、干支暦の一部として使用されました。
十干の10の文字(甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸)は、陰陽の概念によって陽(男性的な性質)と陰(女性的な性質)が交互に配置されています。
そのため、甲・丙・戊・庚・壬は陽に、乙・丁・己・辛・癸は陰に分類されます。
「甲」「乙」「丙」「丁」に含まれる「え」「と」は、それぞれ陽陰を示すもので、この命数法に基づいています。具体的には、「え」は陽を、「と」は陰を表しています。
甲陽(きのえ)、乙陰(きのと)、丙陽(ひのえ)、丁陰(ひのと)といったように、干支暦や陰陽思想における要素を反映するための表現です。

現在日本では、「干支」は十二支のことのみを意味することが一般的です。
猫とねずみの伝説
昔々、天帝(てんてい)は自分の誕生日を祝うために、動物たちを招待しました。
しかし、招待する動物は十二種類に限られていました。
そこで、天帝は動物たちに「明日の朝早くに私の宮殿に来た最初の十二匹の動物を選んで、それぞれに一年を与える」と告げました。
この話を聞いた猫は、自分も十二支に入りたいと思いました。
しかし、猫は朝寝坊な性格だったので、ねずみに明日の朝一番に自分をを起こしてくれるように頼みました。
ねずみは猫の友達だったので、「わかったよ。任せておけ」と答えました。
しかし、ねずみは猫を起こすつもりがありませんでした。
ねずみは自分が一番目に天帝の前に現れて、最初の年を手に入れたいと思っていたのです。
そして、次の日の朝がやってきました。ねずみは早起きして、牛の背中に乗りました。
牛は力が強くて足が速かったので、天帝の宮殿に向かって走り出しました。
その途中で、虎や兎や龍など他の動物たちも加わってきました。
やがて、牛が宮殿に到着しようとしたとき、ねずみは牛の背中から飛び降りて、天帝に一番で挨拶をしました。
天帝はねずみを見て、「お前が一番目か。ではお前に子年を与えよう」と言いました。
そして牛が二番目に来たので、「お前に丑年を与えよう」と言いました。
その後も虎や兎や龍など他の動物たちが順番に来て、それぞれに一年を与えられました。

しかし、猫はまだ眠っていました。やっと目覚めたときにはもう手遅れ…。
十二匹の動物がすでに決まってしまっていました。
猫は慌てて宮殿に向かいましたが、途中でねずみと出会いました。
猫はねずみに「なんで私を起こしてくれなかったんだ!」と怒鳴りました。
ねずみは「ごめんごめん。忘れちゃったよ」と言い訳しました。

猫はねずみの裏切りに激怒して、ねずみを追いかけました。
しかし、ねずみは素早くて逃げられてしまいました。それ以来、猫とねずみは仲が悪くなりました。

ねずみって嫌なやつだな…

この伝説が本当かどうかはわかりませんが、猫が十二支に居ない理由の1つとしてよく語られます。
猫が干支に入っていないのはなぜ?

猫が干支に入れなかった理由にはいろいろな説が存在します。その中から3つご紹介します。
ねずみに騙されて競争に負けた説
昔々、神様が動物たちに自分のところまで競争をするように言いました。
12番目までに到着したものには褒美(干支)を与えると言われた動物たちは神様のもとへ急ぎました。
猫は神様のもとへ向かう途中、川のところでねずみに出会います。
ねずみは猫に「神様のもとへ行くにはこの川を渡るのが一番の近道だ。でも泳ぐことができないから渡れないんだ。」と言います。
それを聞いた猫は、自分も水が苦手だから川を渡ることを諦めて遠回りをすることにしました。
猫の姿が見えなくなると、ねずみは泳いで川を渡りました。
ねずみはまんまと猫を騙して一番に神様のもとへたどり着いたのです。
猫は遠回りをしてせいで12番目までに入ることが出来ませんでした。

この説も猫がねずみに騙されるお話ですね。
お釈迦様の死因が猫のせいだった説
お釈迦さまは80歳でキノコ中毒が原因で体調を崩し、お亡くなりになったと伝わっています。
この時、お釈迦さまはねずみにキノコ中毒に効く薬草を取りに行くように命じました。
しかしその道中、ねずみは猫に食べられてしまい、薬草をお釈迦様に届けることが出来ませんでした。
薬草が届かず、中毒死してしまったお釈迦様は猫を十二支に入れなかったのです。

お釈迦様ごめんなさい…。
干支が誕生した頃まだ猫は身近な存在ではなかった説
干支に動物が割り振られ、表されるようになったのは後漢、王允の時代でした。
中国では後漢の時代にインドから猫が移入してきたと言われています。
そのため、猫はまだ身近な存在ではありませんでした。
まだ民衆に広く猫の存在が知られる前だったため、十二支に入れませんでした。

今は身近な存在ですが、その時代背景を考えると確かにと納得する説ですね。
猫が干支に入っているって本当?

これまでの流れで悲しんでいる猫好きの方、ネコちゃんに朗報です!
アジアには猫が十二支に入っている国もちゃんとあるんです!
チベット、タイ、ベトナム、ベラルーシでは十二支に猫が入っています。
それぞれの国の十二支は下の図の通りです。
| 国 | 干支 |
|---|---|
| チベット | 鼠、牛、虎、猫、龍、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、豚 |
| タイ | 鼠、牛、虎、猫、龍、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、豚 |
| ベトナム | 鼠、水牛、虎、猫、龍、蛇、馬、山羊、猿、鶏、犬、豚 |
| ベラルーシ | 鼠、牛、虎、猫、龍、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、豚 |

うさぎの代わりに猫が入っているようです。
うさぎよりも猫のほうが身近な存在である証拠ですね!
まとめ
十二支は中国から伝わったもので、日本では混同されていますが、本来干支と十二支は別の意味があるものでした。
干支に猫が入れなかった理由は諸説ありましたが、ねずみとの関係を描いたものが多いです。
ねずみが猫を騙したり、逆に猫がねずみを食べてしまったりと、ねずみとの関係の説が多いのは、昔から人間はねずみに悩まされ、猫を飼ってねずみ退治をしていたからではないでしょうか?
また他の国では身近な存在として干支に入っていたり、神聖な生き物とされて干支に入っています。
もし日本でも猫が十二支に入っていたら、どんな年になっていたでしょうか?
猫好きの人は、猫年があったらいいなと思うかもしれませんね!

最後までお読みいただきありがとうございます。
ほかのブログもよろしくお願いします!
-
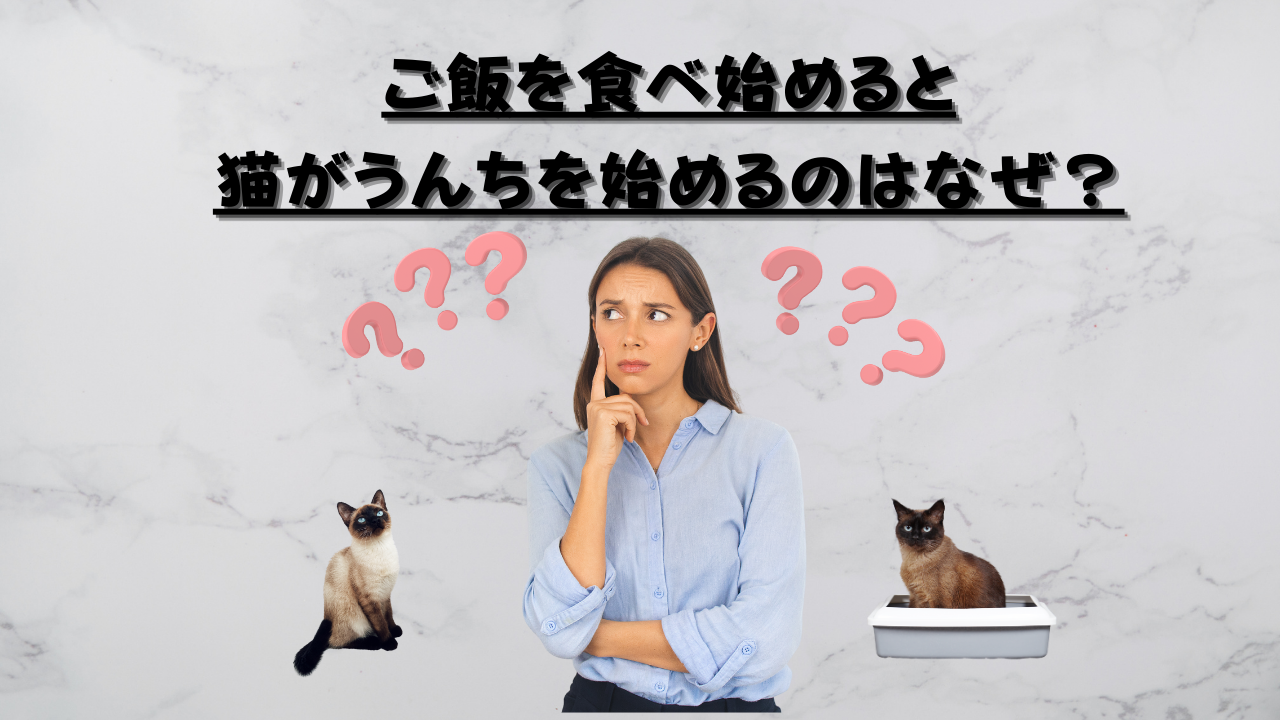
猫の不思議な行動に迫る!飼い主がご飯を食べ始めると、なぜ猫がうんちを始めるのか?
-

猫には魚?それとも肉?
-

猫の大冒険 野良猫と家猫
-

猫の体の秘密大公開!



コメント